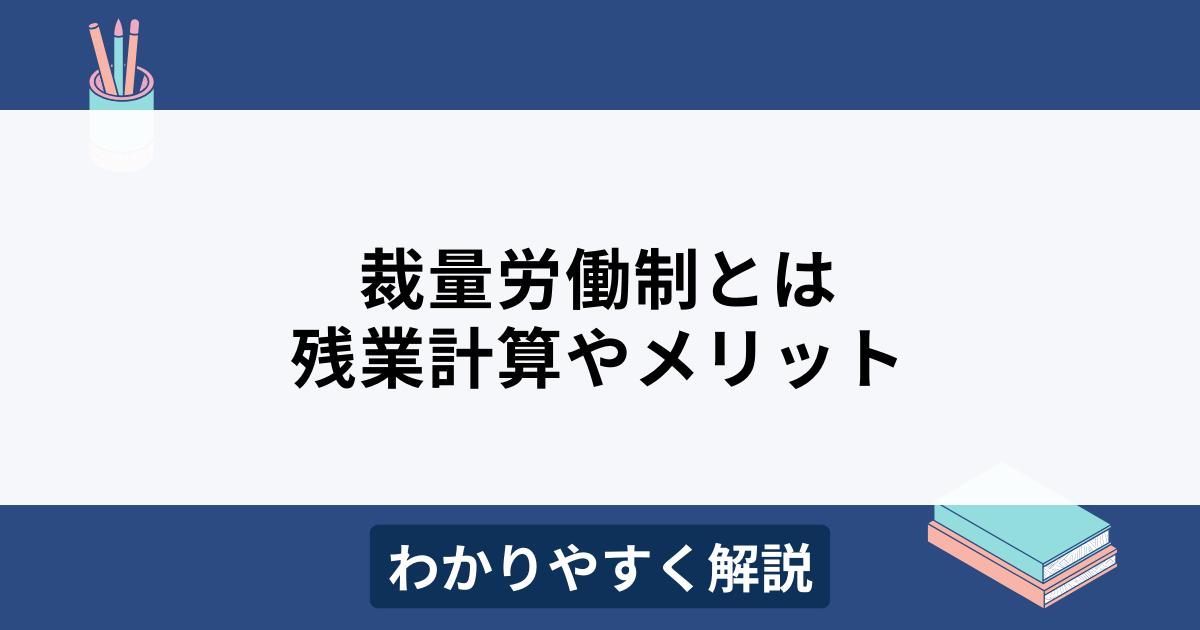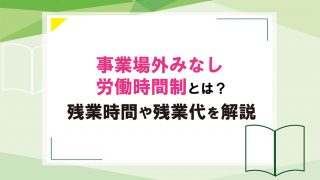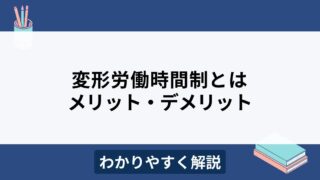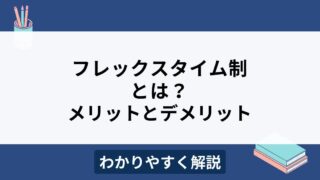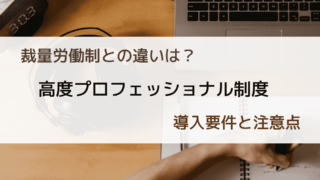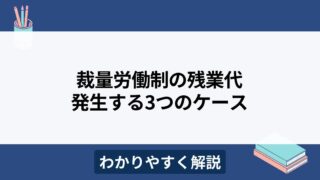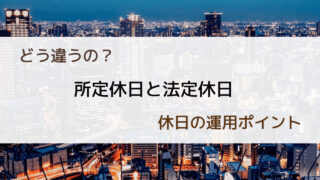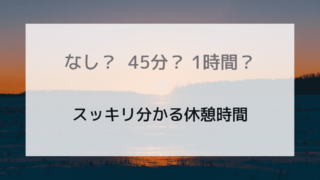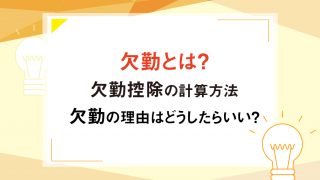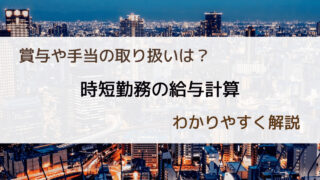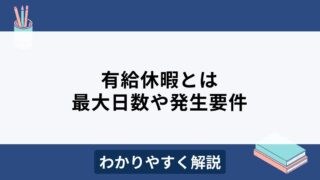裁量労働制は、みなし労働時間制の中の制度で、日々の労働時間を労働者の裁量で自由に決められ、実労働時間に関係なく、あらかじめ設定されたみなし労働時間分働いたものとして扱われます。
働き方改革の議論の俎上にあがったことで注目を集めた裁量労働制ですが、同時に多くの問題点も浮き彫りになりました。そこで2024年4月からはより実効性のある制度となるよう、いくつかの改正が行われました。
この記事では、2024年度の改正内容を踏まえて、裁量労働制のメリット・デメリットや、他の制度との違い、実務上の疑問点などについて、わかりやすく解説します。
勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい
勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
裁量労働制とは
裁量労働制とは、実労働時間に関係なくあらかじめ労使協定で定めた時間分だけ労働したものとみなされる制度です。賃金も実労働時間に関係なく、定めた時間分労働したものとみなして計算します。
労働時間については、会社から指示されるのではなく、労働者本人が決めることができます。労働者は、決められた時間に出勤し、決まった時間まで働くというルールがないため、時間を気にせず働くことができます。
例えば、みなし労働時間を7時間と設定した場合、実労働時間が4時間でも10時間でも7時間働いたとして扱われ、基本的には減給や残業代の対象にはなりません。長時間労働、短時間労働も可能であり、ライフスタイルに合わせて自由度の高い働き方が実現できます。
実労働時間が反映されない点は管理監督者と似ていますが、両者はまったく別の制度であり、裁量労働制はみなし労働時間制の中の制度です。なお、両者の具体的な違いについては後ほど改めて解説します。
裁量労働制には、「専門業務型」と「企画業務型」の2種類があり、それぞれ導入要件や手続きが異なっています。また、2024年4月からは法改正に伴う新制度がスタートするため、この改正点についても後ほど詳しく解説します。
裁量労働制のメリット
裁量労働制のメリットについて、会社側と労働者側のそれぞれの視点から見ていきましょう。
会社側のメリット|人件費の安定、生産性向上
会社側のメリットとして大きいのは、人件費が安定することです。裁量労働制を導入した場合、あらかじめ労使協定で定めた時間分を労働者が働いたとみなして計算し賃金を支払います。
そのため、人件費コストが安定して管理がしやすくなります。ただし、休日出勤や深夜出勤があった場合は、追加で残業代を払う必要があります。
また、生産性の向上も期待できます。従来の制度とは異なり、労働者は残業しても給与が増えないため、より短時間で仕事を終了させるという意識が向上します。
早く仕事を終えることができれば、その分早く帰宅できるというメリットを社員が意識できれば、社員の生産性を上げる動機づけにつながります。
労働者のメリット|柔軟な働き方
労働者にとっては、始業時刻と終了時刻を自由に決めることができ、自分のライフサイクルに応じた働き方ができるというメリットがあります。
また、業務量以上の拘束時間が減るため、仕事の成果をしっかり出せば、短時間で仕事を終了させ、早く帰宅することが可能です。
裁量労働制のデメリット・注意点
続いて、裁量労働制のデメリットや注意すべきポイントについても見ていきましょう。
会社側のデメリット|労務管理や導入手続きが煩雑
人件費の管理は楽になる一方、労働者が始業時刻や終了時刻を決め、自由な時間に働くことになるため、労働者の健康管理や労務管理が極めて難しくなります。
また、労働者ヘの業務の割り当てが、みなし労働時間とつり合いがとれていないケースでは、長時間労働を誘発して習慣化する恐れがあります。
さらに、会社側のデメリットとして大きいのは、導入手続きが非常に煩雑である点です。労使協定の締結・届出や、労使委員会の設置・決議が必要であり、導入するための時間や手間を要することは避けられません。
労働者のデメリット|残業代の減少、長時間労働のおそれ
労働者にとっては、繁忙期や業務が多い日でも、実労働時間に関係なく残業代が出ないのがデメリットです。導入前と比較すると、賃金総額はおおむねダウンします。
また、長時間労働に陥りやすく、とくに自己管理能力の乏しい労働者は生産性が上がらないため、その傾向が強くなります。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
裁量労働制における2024年4月からの改正点
裁量労働制は、法改正法を受けて2024年4月から制度の内容がいくつか変更されます。主な改正ポイントについて見ていきましょう。
専門業務型裁量労働制の対象業務が追加
専門業務型裁量労働制は、その対象とできる業務が限定的に列挙されており、対象業務以外を専門業務型裁量労働制の対象とすることはできません。
今回の改正では、従来の19業務(後述します)に加え、「銀行または証券会社における顧客の合併および買収に関する調査または分析およびこれに基づく合併および買収に関する考案および助言の業務」(いわゆるM&Aアドバイザー)が対象業務となりました。
対象者の同意及び同意撤回手続きについて
専門業務型裁量労働制においては従来、個別に対象労働者の同意を得ることは要件とされていませんでした、今回の改正により、個別に同意を得ること及び同意を拒んだことを理由とする不利益取り扱いの禁止が義務付けられました。
また、専門業務型・企画業務型のいずれについても、労働者本人の同意撤回手続きと同意及び撤回の記録保存に関する定めが義務付けられました。
企画業務型裁量労働制の労使委員会について
企画業務型裁量労働制において、対象労働者に適用される賃金・評価制度について労使委員会への説明が義務付けられました。また、労使委員会の運営規程に「制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項(制度の実施状況の把握の頻度や方法など)」を追加することも義務付けられました。
労使委員会の開催については、従来は特に規定ありませんでしたが、今回の改正により開催頻度を6ヶ月以内ごとに1回とする必要があります。
企画業務型裁量労働制の定期報告について
企画業務型裁量労働制の定期報告について、従来は労使委員会の決議の日から6ヶ月以内ごとに1回労働基準監督署への報告が義務付けられていましたが、これが「労使委員会の決議の日から起算して初回は6ヶ月以内に1回、その後1年以内ごとに1回」に変更されました。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
裁量労働制は2種類|かんたん比較
専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制は、労働時間の取扱いについては同じですが、対象業務、対象事業場、導入手順などに違いがあります。
とくに、企画業務型裁量労働制を導入する場合は、労使委員会の設立と決議が必要になる点と、導入後も労働基準監督署への報告が必要になる点が、専門業務型裁量労働制と大きく異なります。
| 専門業務型裁量労働制 | 企画業務型裁量労働制 | |
|---|---|---|
| 対象業務 | 業務の性質上、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難な業務 (対象20業務は後述) | 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査、分析の業務であって、業務の性質上、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をしない業務 |
| 対象事業場 | 対象業務のある事業場 | 企業全体に影響を及ぼす事業運営上の重要な決定が行われる事業場 (本社や本店など事業運営上の重要事項を決定する事業場) |
| 対象労働者 | 対象業務に従事する労働者であって、この制度によることに同意したもの | 対象業務に従事する労働者であって、この制度によることに同意したもの |
| 導入手順 | 労使協定を締結し、所轄労働基準監督署に届け出る | 労使委員会の委員の5分の4以上の多数により議決された決議内容を所轄労働基準監督署長に届け出る |
| 事後手続き | なし | 決議が行われた日から起算して初回は6ヶ月以内に1回、その後1年以内ごとに1回、所轄労働基準監督署長へ定期報告を行う |
専門業務型裁量労働制とは
専門業務型裁量労働制は、労働基準法第38条の3に基づく制度です。
業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として定められた業務から対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使協定であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。
専門業務型裁量労働制の要件
専門業務型裁量労働制の対象となるのは、以下の20業務です。
- 新商品・新技術の研究開発、または人文科学・自然科学の研究の業務
- 情報処理システムの分析・設計の業務
- 新聞・出版の事業における、記事の取材・編集の業務、放送番組の制作のための取材・編集の業務
- デザイナーの業務
- 放送番組、映画等の制作の事業における、プロデューサーまたはディレクターの業務
- コピーライターの業務
- システムコンサルタントの業務
- インテリアコーディネーターの業務
- ゲーム用ソフトウェアの創作業務
- 証券アナリストの業務
- 金融工学等の知識を用いる金融商品の開発業務
- 大学での教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る)
- 銀行または証券会社における顧客の合併および買収に関する調査または分析およびこれに基づく合併および買収に関する考案および助言の業務
- 公認会計士の業務
- 弁護士の業務
- 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
- 不動産鑑定士の業務
- 弁理士の業務
- 税理士の業務
- 中小企業診断士の業務
専門業務型裁量労働制の導入手順
専門業務型裁量労働制の導入手順は、以下の通りです。
- 下記の事項を全て明記した労使協定を定める
- 対象業務(対象20業務)
- みなし労働時間(対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間)
- 対象業務を遂行する手段や時間配分の決定等に関し、対象労働者に具体的な指示をしないこと
- 対象労働者の労働時間の状況の把握方法と把握した労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容
- 対象労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容
- 制度の適用に当たって労働者本人の同意を得ること
- 制度の適用に労働者が同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしないこと
- 制度の適用に関する同意の撤回の手続
- 協定の有効期間(3年以内とすることが望ましい)
- 労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理の実施状況、同意及び同意の撤回の労働者ごとの記録を協定の有効期間中及びその期間満了後5年間(当面は3年間)保存すること
- 労使協定を管轄の労働基準監督署に届け出る
- 対象労働者の個別同意を得る
- 労使協定を労働者に周知する
企画業務型裁量労働制とは
企画業務型裁量労働制は、本社や本店など事業運営の決定権を持つ事業場の対象業務につく労働者に対して、労使委員会であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。専門業務型と違って、要件を満たす事業場の労働者であれば、ある程度幅広い労働者が対象者になり得ます。
企画業務型裁量労働制の要件
事業運営にとっての重要事項の決定権をもつ立場を利用し、企画業務型裁量労働制そのものが、恣意的に運用される恐れがあります。そのため、労使委員会の決議など、専門業務型よりも厳格な導入手続きが要求されています。
対象業務とするには、以下の4要件が必要です。
- 事業の運営に関する事項についての業務であること。
- 企画、立案、調査および分析の業務であること
- 業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務であること
- 業務の遂行の手段および時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないことと業務であること
企画業務型裁量労働制の導入手順
企画業務型裁量労働制の導入手順は下記のとおりです。
- 以下の要件に沿って労使委員会を設置する
- 委員会の委員の半数は、事業場にある労働者の過半数で組織する労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者に任期を定めて指名されていること
- 委員会の議事において、議事録が作成・保存されるとともに労働者に対する周知が図られていること
- 労使委員会にて出席している労使委員の5分の4以上の多数により、以下の事項を決議する
- 対象業務
- 対象労働者の範囲
- みなし労働時間
- 対象労働者の健康・福祉確保の措置の具体的内容
- 対象労働者からの苦情処理のために実施する措置の具体的内容
- 制度の適用に当たって労働者本人の同意を得ること
- 制度の適用に労働者が同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしないこと
- 制度の適用に関する同意の撤回の手続
- 対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明を行うこと
- 労使委員会の決議の有効期間
- 労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理の実施状況、同意及び同意の撤回の労働者ごとの記録を協定の有効期間中及びその期間満了後5年間(当面は3年間)保存すること
- 労使委員会の決議を所轄の労働基準監督署長に届け出る
- 対象労働者の個別同意を得る
- 制度を実施し、決議の日から初回は6か月以内ごとに1回、以降は1年以内ごとに1回、所轄労働基準監督署長へ定期報告を行う
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
裁量労働制とほかの制度との違いは?
裁量労働制は、メリット・デメリットという観点からほかの類似した労働時間制と比較することが大切です。
裁量労働制と事業場外みなし労働時間制との違い
事業場外みなし労働時間制は、裁量労働制と同じ「みなし労働時間制」のひとつです。事業場外労働みなし労働時間制とは、外まわりの営業職など事業場外で労働する場合に導入される制度です。
事業場外で業務に従事しており、かつ使用者の具体的な指揮監督ができずに労働時間を算定するのが困難な業務が対象になります。裁量労働制のように、対象業務が制限されていないのも特徴です。
| 裁量労働制 | 事業場外みなし労働時間制 | |
|---|---|---|
| 対象労働者 | 専門業務型は対象業務、企画業務型は対象事業場が限定される | 事業場の外で業務に従事する者(外回りの営業職や記者など) |
| 労働時間 | 協定または委員会決議で定めた時間が労働時間となる | 所定労働時間+業務上通常必要とされる時間 |
| メリット | 労働時間の管理がしやすい | 職種や事業場による制限がない |
| デメリット | 適用のハードルが高い | 「労働時間を算定しがたい事業場外業務」を巡って労使トラブルに発展しやすい |
裁量労働制と変形労働時間制との違い
変形労働時間制とは、1ヶ月や1年単位で労働時間を柔軟に調整する制度です。変形労働時間制には、1年間単位、1カ月単位、1週間単位、フレックスタイム制の4種類がありますが、このうちフレックスタイム制は、内容が大きく異なるため別で解説します。
変形労働時間制は就業規則や労使協定で定めた範囲で、対象期間内の繁閑に応じて労働日や1日の所定労働時間を調整できる制度であるため、裁量労働制のように労働者自身が日々の労働時間を自由に設定できるわけではありません。
また、裁量労働制においては基本的に時間外労働が発生しませんが、変形労働時間制においては所定労働時間の定めに応じて時間外労働が発生します。
裁量労働制とフレックスタイム制との違い
裁量労働制もフレックスタイム制も、労働時間の設定と管理が労働者に委ねられるという点は同じですが、フレックスタイム制では「みなし労働時間」の設定がありません。また、フレックスタイム制においては、必ず出勤すべき時間帯であるコアタイムが設定されることがあります。
よって、労働者はフレックスタイム制で定められた所定労働時間を必ず労働する必要があります。また、フレックスタイム制では対象労働者の制限はありません。
| 裁量労働制 | フレックスタイム制 | |
|---|---|---|
| 対象労働者 | 専門業務型は対象業務、企画業務型は対象事業場が限定される | 制限なし |
| 所定労働時間 | みなし労働時間が所定労働時間となる | 清算期間内の所定労働時間の中で労働時間を調整する |
| 時間外労働 | 基本的に発生しない | 実労働時間が清算期間内の所定労働時間を超えた部分が時間外労働となる |
| メリット | 労働時間の管理がしやすい | 幅広く適用でき、所定労働時間と実労働時間の差分が賃金に反映される |
| デメリット | みなし労働時間と実労働時間の乖離が大きいと、労働者からの反発を招く | 労働者によっては時間管理がルーズになる |
裁量労働制と高度プロフェッショナル制度との違い
高度プロフェッショナル制度とは、一定の年収要件を満たす高度な専門知識を持っている労働者を対象に、原則、労働時間に関する制限を撤廃する制度です。
高度プロフェッショナル制度は、より業務が限定され、基本的に労働基準法の適用が及ばないのが特徴です。
| 裁量労働制 | 高度プロフェッショナル制度 | |
|---|---|---|
| 対象労働者 | 専門業務型は対象業務、企画業務型は対象事業場が限定される | 高度の専門的知識等を要する4業務に限定され、年収要件もある |
| 休日手当 深夜労働手当 | 割増賃金の対象となる | 発生しない |
| メリット | 労働者の技能や年収によって適用が左右されない | 能力成果主義によって生産性が向上する |
| デメリット | みなし労働時間の時間設定が短過ぎると、生産性が低下する | 労働基準法を逸脱する長時間・連続勤務を誘発する |
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
裁量労働制についてよくある質問
裁量労働制について、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。
- Q裁量労働制では残業代は発生しない?
- Q裁量労働制で休憩時間はどう与える?
- Q裁量労働制で欠勤や遅刻・早退があったら?
- Q裁量労働制でも短時間勤務(時短勤務)は可能?
- Q裁量労働制で年次有給休暇はどう扱う?
裁量労働制の導入には、勤怠管理システムが必須
裁量労働時間制を導入することで残業代の計算が楽になるとはいえ、休日出勤、深夜労働の把握や長時間労働に対するメンタルヘルスケアなど労働時間の管理は必要です。
また、適切なみなし労働時間を設定するには、勤怠管理システムによる定量的な分析が非常に有効です。裁量労働制をスムーズな運営に、勤怠管理システムは不可欠です。
勤怠管理システムの選定・比較ナビをご利用頂くことで、裁量労働制の導入・運用をサポートしてくれる勤怠管理システムの中から、御社にマッチするシステムを探し出すことができます。
勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい
勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。