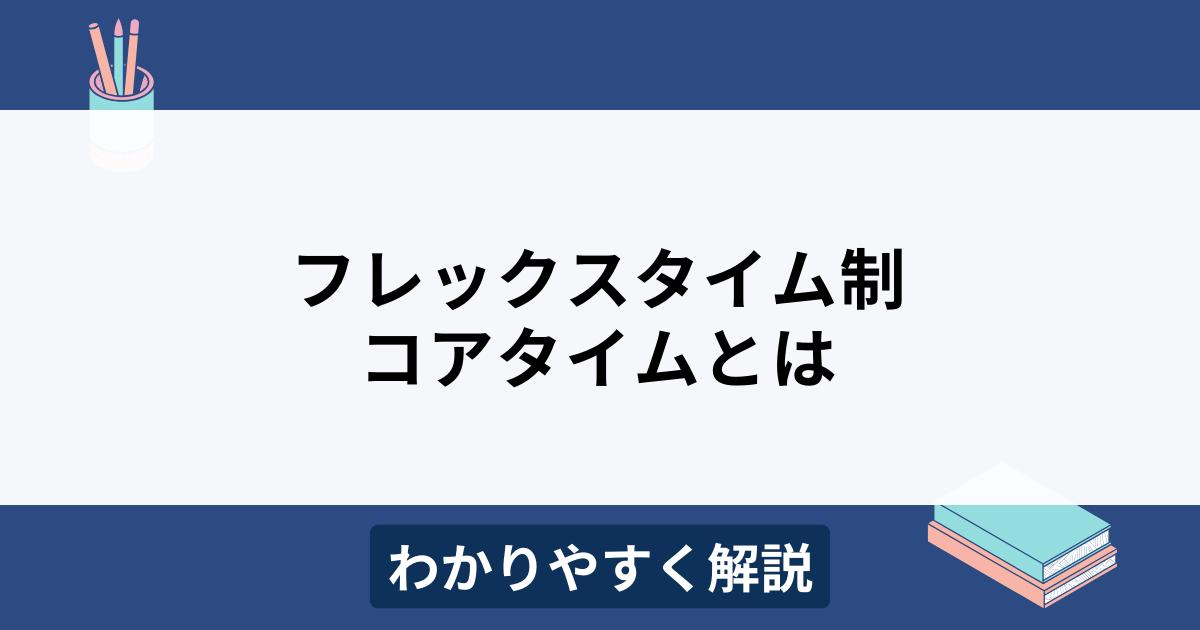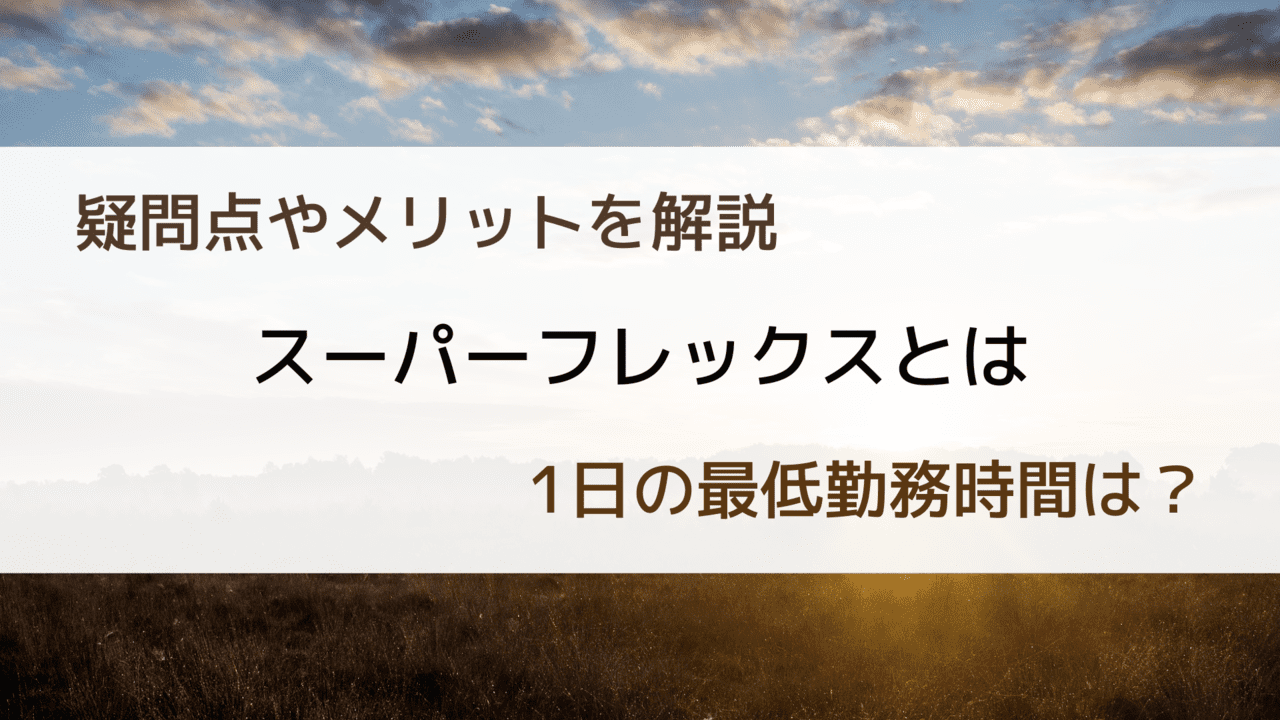労働時間を労働者に委ねるフレックスタイム制において、使用者の意思を反映できるのがコアタイムの設定です。適切なコアタイムの設定は、フレックスタイム制のスムーズな運用につながります。
コアタイムを設けないスーパーフレックスを採用する企業も増えていますが、業態や取引先との関係によってはコアタイムを設ける必要が出てきます。
「コアタイムの平均的設定時間」などの統計情報を鵜吞みにして、採用率の高い時間帯をそのまま自社にも適用してしまうと、制度そのものが立ち行かなくなる可能性もあります。
コアタイムの本来の目的を見失わないためにも、自社にマッチしたコアタイムの設定を見極めることが大切です。
勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい
勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
フレックスタイム制のコアタイム、フレキシブルタイムとは
フレックスタイム制において、就業時間のうち、会社が必ず出勤しなければならない時間帯として指定した時間をコアタイムといいます。
一方、コアタイム以外の労働者が自由に出退勤を決められる時間帯をフレキシブルタイムといいます。
コアタイムやフレキシブルタイムを設定するかどうかは任意ですが、設定する場合は労使協定で定める必要があります。
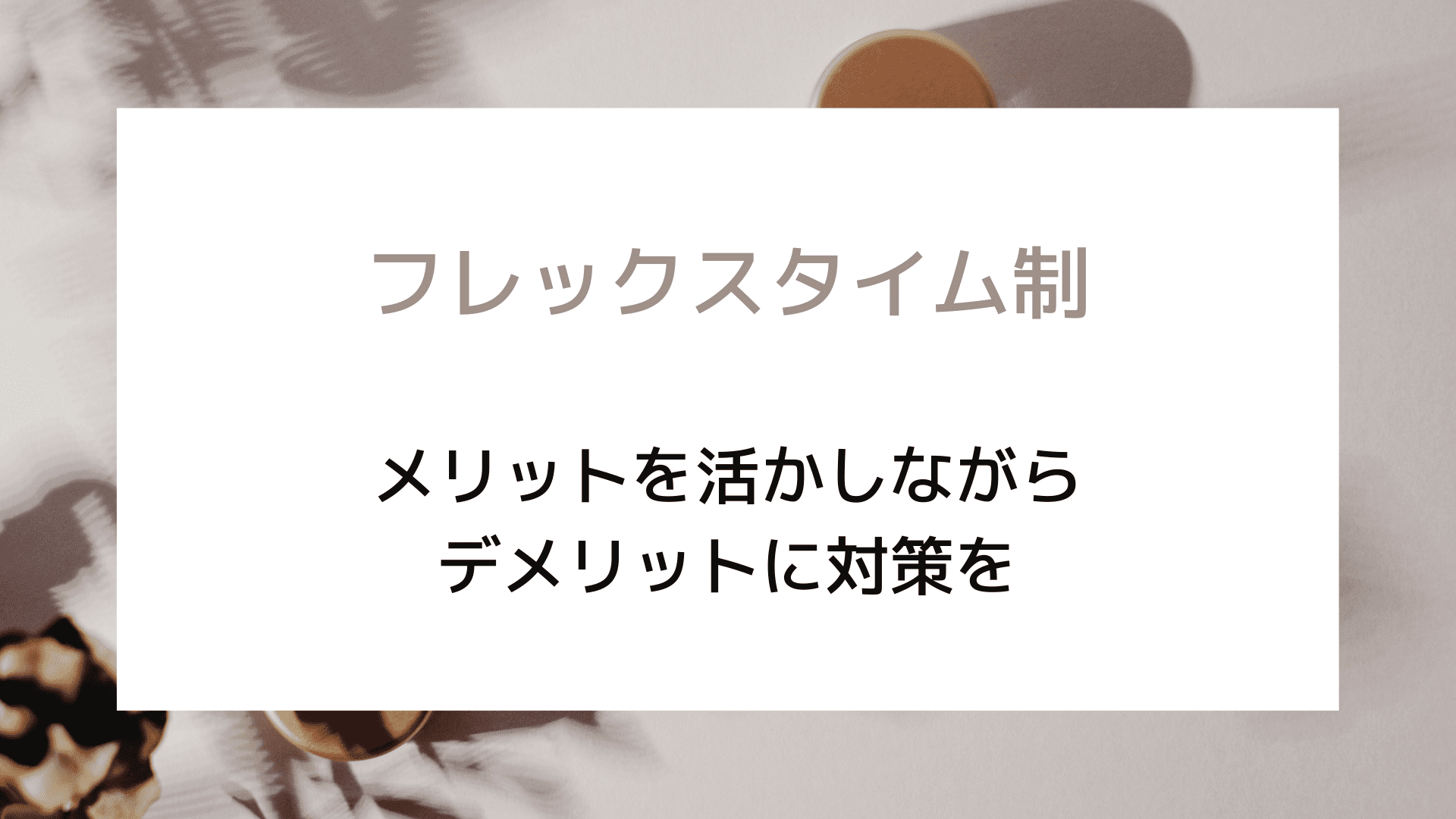
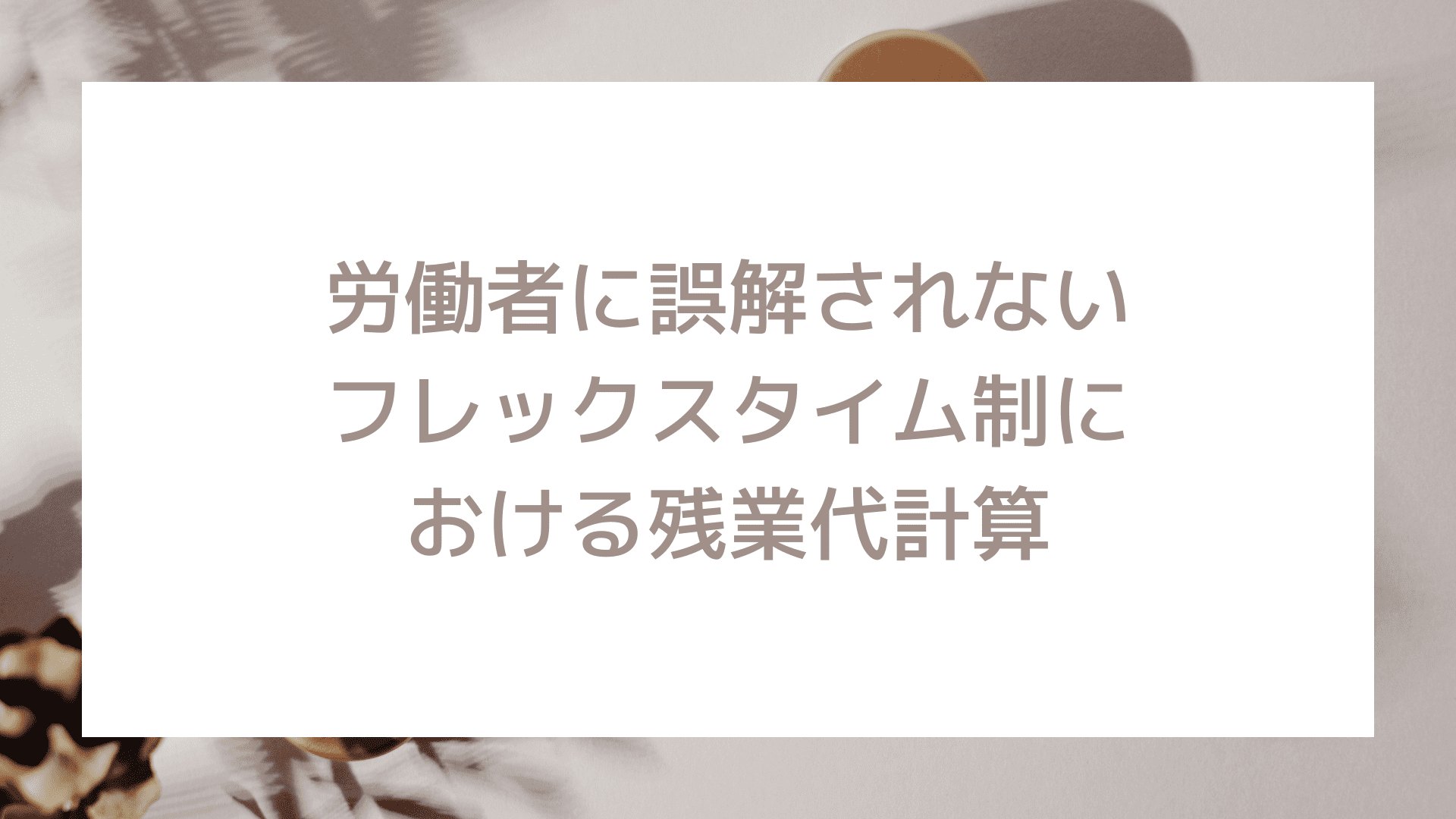
コアタイムの平均は?何時間がベスト?
コアタイムの平均は4時間~4時間半程度とされています。公的な統計データは20年ほど前のものしかありませんが、現在においても大きな変動はありません。
法的に何時間までという具体的な決まりは無いものの、設定次第によっては、法令違反に問われるケースや、フレックスタイム制そのものが否認される恐れがあります。一概にベストな時間というものは言えませんが、4~6時間程度に設定するのが無難でしょう。
コアタイムが認められないケース
フレキシブルタイムに対するコアタイムの割合が、フレックスタイム制の意義を失わせるほど大きい場合、フレックスタイム制とは認められません。
例えば、コアタイム(9:30~17:00)、フレキシブルタイム(9:00~9:30、17:00~17:30)のように大半がコアタイムで、フレキシブルタイムが極端に短いような設定はできません。
コアタイムの開始から終了までの時間と、標準となる1日の労働時間がほぼ一致しているような場合も、フレックスタイム制とは認められません。
公的に具体的な基準は示されていませんが、労働時間の4分の3がコアタイムのようなケースは認められない可能性が高いと言えます。
また、フレキシブルタイムの時間帯が30分単位となっており、その中から始業時刻もしくは終業時刻を選択するような制度は、労働者が自主的に労働時間を設定しているとはいえず、フレックスタイム制の趣旨に反するため認められません。
フレックスタイム制は、始業時刻と終業時刻の両方を、労働者が設定できる制度でなければなりません。
業務に支障が出ないコアタイムの設定
コアタイムは、担当者が一堂に会する会議や取引先との対応など、会社の業務にとってどうしても不在では困るという時間帯に限定することをおすすめします。
フレックスタイム制を導入する際、典型的なデメリットとして挙げられるのが、取引先などの社外対応です。フレックスタイム制を導入後、コアタイムと社外対応が多い時間帯が異なっていると、トラブル増加や社外からの信頼を落としかねません。
導入する場合には、事前に対応部署に対して、対外的な依頼が多い時間帯などをリサーチしておくことが重要です。
コアタイムはなしにできる?
コアタイムを一切設定しないことも可能であり、これを「フルフレックス」や「スーパーフレックス」といいます。
コアタイムなしのフレックスタイム制と裁量労働制はどう違う?
スーパーフレックス(フルフレックス)であっても、あくまでも労働者に始業・終業時間を委ねるフレックスタイム制であることには変わりありません。よって、実労働時間分の賃金が発生し、実労働時間が所定労働時間に足りなければ控除の対象となります。
対して、裁量労働制において労働者に委ねられるのは「業務の遂行方法」であり、出退勤の自由ではありません。労働時間は、あらかじめ決められたみなし労働時間で管理されます。
よって、実労働時間がみなし労働時間に足りなくても控除はできず、超過しても割増賃金は発生しないことになります。ただし、欠勤の場合は、みなし労働時間が適用されないため、欠勤控除可能です。
また、フレックスタイム制が広く一般の労働者に適用可能であるのに対し、裁量労働制は適用できる業務などが限定されている点も、大きな違いといえます。
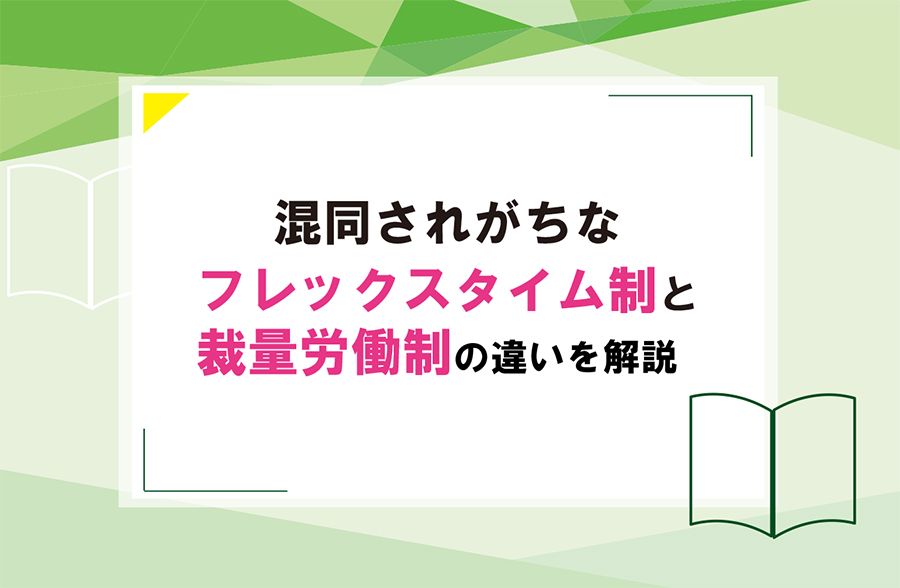
フレキシブルタイムの決め方は?
労働者の自由度を尊重しつつ、セキュリティやコスト面で負担とならないよう、現実的な範囲でフレキシブルタイムを設定するのが理想的です。フレキシブルタイムは幅が広ければ広いほど自由度が高まるため、労働者にとってのメリットは大きくなります。
しかし、フレキシブルタイムがあまりにも長い時間帯で設定すると、会社側にとってセキュリティ上のリスクや光熱費コストの大幅増につながるというデメリットが出てきます。
また、終業時間の範囲を遅い時間まで取ってしまうと、深夜労働の割増賃金が発生してしまうため注意が必要です。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
ケースで考えるコアタイムの設定方法
コアタイムで設定されやすい時間帯としては、中間的な時間の10:00~15:00が一般的といわれています。
しかし、業務が忙しい時間帯は会社の業態や取引先との関係などによって、会社ごとにバラバラです。それぞれの会社にとって、最も適切で有効なコアタイムは変わってきます。
コアタイムの具体的な設定例を、以下に3つご紹介します。
- ゆっくり出勤してもらい、午後に業務を集中させる
- 深夜労働にならない程度にフレキシブルタイムを幅広く取る
- 曜日によってコアタイムの設定を変える
ゆっくり出勤してもらい、午後に業務を集中させる
新型コロナウィルス感染症などの予防対策もあり、昨今、始業時間を10時以降に設定する会社が増えています。
それに伴って、顧客や取引先とコンタクトを取る時間帯が後ろ倒しになり、午後に集中するような業種も増えています。
このような状況から、思い切ってコアタイムを後ろにずらすことで、フレックスタイム制の導入効果をさらに上げることが期待できます。コアタイムを正午以降に設定し、マンパワーを午後に集中させるのも一つの方法です。
労働者にとっては、朝の通勤ラッシュが回避でき、午前中はゆっくり出勤できるようになるため、労働者の心身のバランスは良くなり、仕事のモチベーションアップにもつながるでしょう。
午後に専念できる環境が整備されれば、労働者の仕事に対する集中力もアップしますので、会社全体の生産性向上につながるようになればベストです。
【設定例】
フレキシブルタイム:9~12時、16~20時/コアタイム:12~16時
深夜労働を避けつつフレキシブルタイムを幅広く取る
得意先などの外部対応があるため、コアタイムを設定せざるを得ない会社は多いです。ただし、なるべく労働者の要望に合ったフレックスタイム制を運用したい場合には、フレキシブルタイムを幅広く設定するのも一つの方法です。
幅広いフレキシブルタイムになると、前述のとおり、社内セキュリティ上の問題や光熱費のコスト負担増、早朝や深夜残業の増加、自己管理能力が低い労働者の場合は、無駄な残業時間が増加するなどのリスクは確かに伴うのは事実です。
しかし、これらのデメリットはそれぞれの対策を講じることで対応可能です。また、自由度が高いフレックスタイム制によって、労働者はいきいきと働くことが可能になり、仕事に対するモチベーションアップが期待できます。
【設定例】
フレキシブルタイム:6~11時、15~21時/コアタイム:11~15時
曜日によってコアタイムの設定を変える
コアタイムは曜日ごとに変えることも可能です。週一回は社内会議を設定したい、取引時からの要請や依頼が毎週決まった曜日に集中するといった曜日ごとに傾向がある場合などには効果を発揮します。
また、コアタイムを設定する曜日と、設定しない曜日を設けるのも可能です。
【設定例】
<月曜日・金曜日>フレキシブルタイム:7~10時、12~19時/コアタイム:10~12時 <その他の曜日> フレキシブルタイム:7~19時/コアタイムなし
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
フレックスタイム制のコアタイムでよくある質問
フレックスタイム制のコアタイムに関して、よく寄せられる質問をQA形式でまとめました。
- Qコアタイムに遅れたら遅刻にできる?
- Qコアタイムに時間単位年休を取得できる?
フレックスタイム制の運用には、勤怠管理システムが必須
業種や会社ごとに経営環境は異なるように、フレックスタイム制におけるコアタイムやフレキシブルタイムの適切な設定は会社ごとに異なります。始業時刻や終了時刻など、働く時間帯を労働者に委ねるとしても、その管理は使用者側が行わなければなりません。
適切なコアタイムを検討するには、業務状況分析や実労働時間管理が重要であり、これらを自動化してくれる勤怠管理システムの導入は不可欠です。
フレックスタイム導入や改定の際、ぜひ勤怠管理システムの同時導入をおすすめします。勤怠管理システムの選定・比較ナビでは、豊富に各社の勤怠管理システムを紹介していますので、ぜひご覧ください。
勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい
勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。