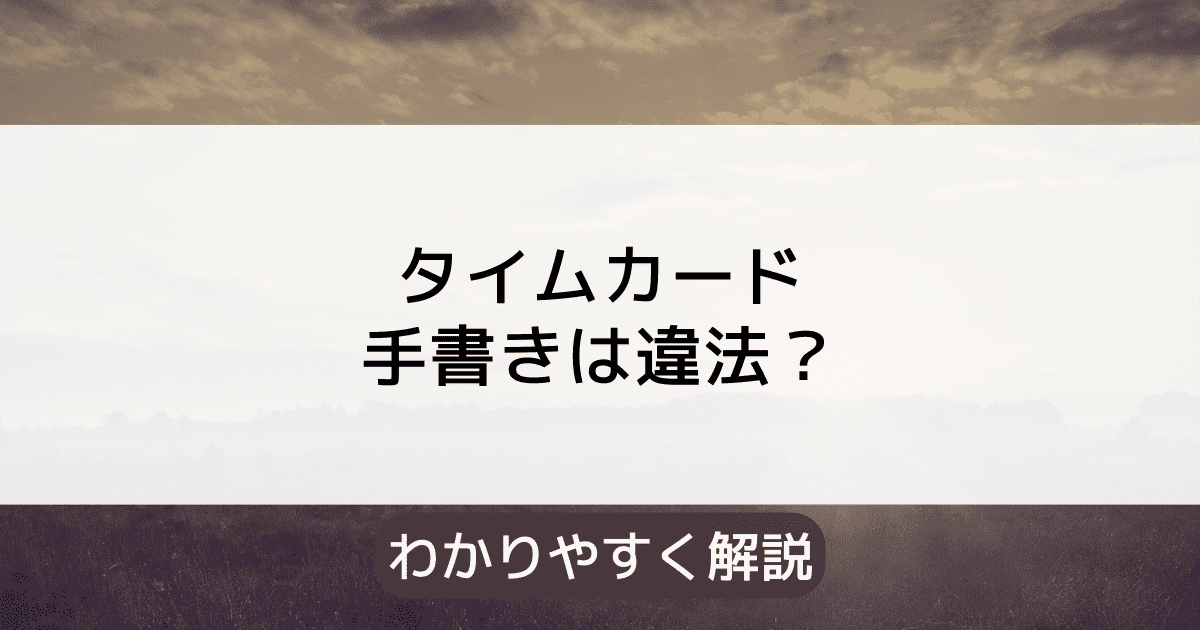勤怠管理は急速にシステム化が進む一方で、依然としてタイムカードを利用している会社も少なくありません。中には、打刻機ではなく、タイムカードに直接手書きしているケースも見受けられます。
もちろん、適切に管理されている以上は、手書きのタイムカードであっても違法性を問われるわけではありません。ただし、手書きのタイムカードにはさまざまなリスクが存在するのも、また事実です。
この記事では、タイムカードを手書きで管理することの問題点や、その解決策についてわかりやすく解説します。
勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい
勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
タイムカードとは
タイムカードは、まだコンピューターが普及していない頃から行われている出勤時間と退勤時間を記録している紙のことを挿しますが、広い意味では紙に打刻するう機械のことも含めてタイムカードと呼ぶ事もあります。
機械を使って打刻する事もあれば、手書きで紙に書く事もありますが、手書きの場合はあまりタイムカードとは呼ばないことが多いです。
使い方
タイムカードは専用の少し厚い紙を機械にいれることで、時間がスタンプのように押されます。機械に対しての専用の紙であることで、曜日や出勤時に押す場所や退勤時に押す場所が正確になります。
お昼休みに入った時間と、終わった時間も打刻することもあります。大抵の場合、不正防止のためマネージャーが毎日出勤時間と退勤時間が間違ってないかチェックをします。
また、機械に表示される時間もパスワードを入力しないと変えられないようにするなど、不正防止のための機能も付いていたりします。最近では電波時計で、自動的に正確な時間に調整してくれるタイプも出ています。
保存期間と計算
タイムカードに書かれてある時間を全て合わせて、給料を一人づつ計算しなければなりません。さらに、単純な足し算と掛け算ではなく、残業手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、交通費などを絡ませて計算しなければなりません。
最近はパソコンに送信して一瞬で計算したり、タイムカードに打刻する機械の中で計算してくれる機能がついているものもあるので、計算はだいぶ楽になりました。
なお、タイムカードは3年間の保存義務がありますが、パソコンの中に全ての従業員の勤務情報を取り込んでいるとタイムカードは破棄しても問題ありません。従業員の数が多くなると、保存しなければならない紙の量も大量となってしまいます。
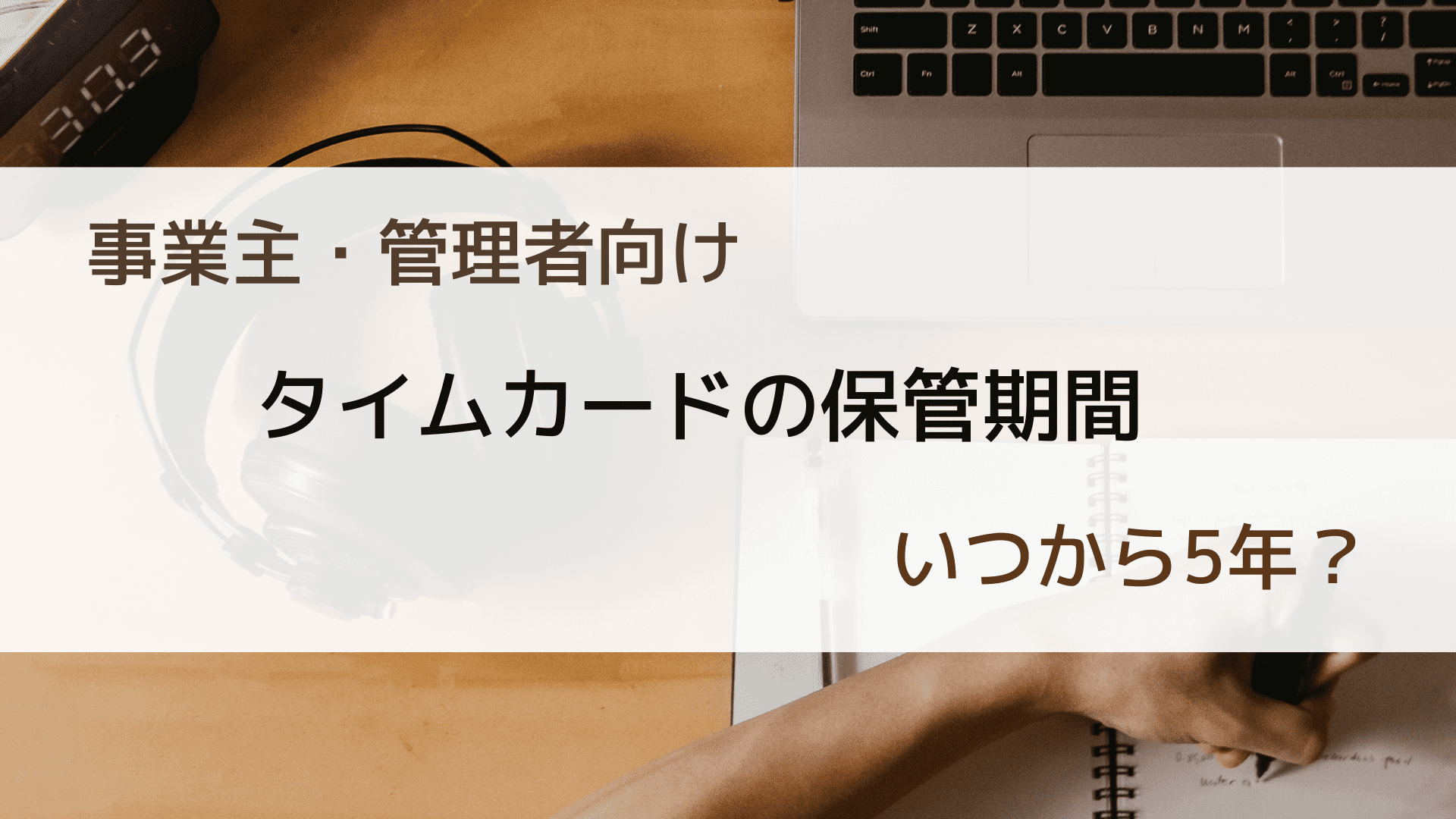
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
手書きのタイムカードは違法?
勤怠実績を正しく反映できている限り、手書きのタイムカードで勤怠管理を実施していても、違法ではありません。ただし、手書きのタイムカードは、改ざんや計算ミスが起こる確率が高く、正確性や客観性の担保が難しいという問題点があります。
2019年4月から施行されている働き方改革関連法によって、労働安全衛生法が改正され、客観的な労働時間の把握が企業に義務付けられました。従業員一人ひとりが1日何時間働いたか、毎日の労働時間を適正に記録する義務が、会社に課せられています。
厚生労働省は、原則的に以下の方法に基づいて日々の労働時間を記録するよう、求めています。
- 使用者が自ら現認すること
- タイムカード、ICカード、PCの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として 確認し、適正に記録すること
タイムカードや出勤簿に「手書き」で記録することは、あくまでも自己申告であり、従業員のモラルに依存する形となるため、上記の客観的な記録とはみなされません。
手書きのタイムカードのメリット
タイムカードの手書きは、推奨される記録方法ではないものの、以下のように一定のメリットはあります。
- 導入・運用コストを抑えられる
- 誰でも簡単に利用できる
導入・運用コストを抑えられる
手書きのタイムカードで勤怠管理を行う場合、初期費用やランニングコストがほとんど掛かりません。出退勤時刻の打刻や労働時間は全て手書きで管理するため、新たに設備を購入する必要はなく、紙代とファイル代くらいで済むでしょう。
一方で勤怠管理システムを導入した場合は、初期費用や専用端末代、月額利用料などが必要となってきます。単純にコスト面だけで言えば、手書きのタイムカードの方が安く抑えられます。
誰でも簡単に利用できる
基本的に、会社指定のフォーマットに出退勤時刻を記載するだけなので、誰でも簡単に利用できます。
ITリテラシーが低い従業員や、日本語に慣れていない外国人スタッフが在籍している場合でも、スムーズに対応できます。
手書きのタイムカードのデメリット
手書きのタイムカードは、以下に挙げるようなデメリットがあります。やはり、メリットよりもデメリットの方が大きいことが、お分かりいただけると思います。
- 客観的な記録として認められない
- 計算ミスが起こりやすい
- 改ざんされやすい
- 多様な働き方に対応できない
- 資料の保管が煩雑になる
客観的な記録として認められない
手書きのタイムカードは、あくまでも自己申告に過ぎないため、厚生労働省の定める「原則的な客観的な記録」としては認められません。
かりに、残業代未払いや違法な長時間労働などの労使トラブルが発生した場合、労務管理資料としての価値が弱いため、会社側の主張が認められない可能性も高くなります。
計算ミスが起こりやすい
手書きの場合は、文字や数字が判読できないことがあり、本人に再確認が必要となるなど、無駄な手間が発生します。月次でまとめて集計する際に確認しようとしても、書いた本人が覚えていないケースも珍しくありません。
また、別の台帳やエクセルなどに転記する際にミスしたり、手計算でミスが発生したりと、誤った情報で給与計算が行われるリスクがあります。その結果、給与の一部未払いや過払いといった重大な問題に発展する可能性もあります。
改ざんされやすい
手書きのタイムカードは誰でも利用できる反面、書き換えも簡単にできます。残業時間の過剰申告や遅刻した際のもみ消しなど、労働者側にとって都合の良い形に勤怠データを書き換えられるリスクがあります。
また反対に、使用者側が残業時間を不当に削ったり無かったことにすることも可能であるため、労使間に余計な猜疑心を生んでしまうことにもなります。
多様な働き方に対応できない
外回りの営業職や現場で働く作業員など、オフィス外で働く機会が多い労働者は、タイムカードを記入するためだけに帰社しなければならず、無駄な移動時間が発生します。
こうした移動時間は、基本的に労働時間に含まれるため、会社側にとっても無駄なコストが発生していることになります。
また、近年急増している在宅勤務やリモートワークも、手書きのタイムカードでは対応できないということになります。
資料の保管が煩雑になる
タイムカードなどの出勤状況を記録した書類は、賃金台帳などと共に5年間の保存が義務づけられています(現在は経過措置により、3年間でも差し支えありません)。
そのため、紙の資料であるタイムカードは、保管に物理的スペースが必要となります。また、いざという時に必要な情報を探すのが、非常に手間がかかることにもなります。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
タイムカードを手書きする場合の実務上のポイント
本記事では勤怠管理システムを導入することをオススメしますが、従業員が数名程度の事業場であれば、タイムカードの方が楽な場合もあります。また、現実的に費用などの面で、システム導入が難しいケースもあると思います。
そこで、タイムカードを手書きで運用する場合に注意すべきポイントについて、解説していきます。
タイムカード修正のルールを決める
改ざんによる不正が起こらないよう、一度記録したタイムカードを修正する場合のルールを決めましょう。
たとえば、「修正する際は上長の許可を得ること」「保管は従業員個人ではなく、管理者が取りまとめること」などが有効でしょう。
できる限り使用者自ら現認する
手書きのタイムカードは、記入後すぐに管理者まで提出させて、その場で確認することも重要です。
また、使用者側も改ざんしていないことを証明するため、集計などの際には従業員にも再度確認してもらうのも良いでしょう。
勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ
・システム検討時に注意すべき点を整理したい
・システムにより効率化できる点を整理したい
・システムの運用で注意すべき点を整理したい
勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。
タイムカードの手書きについてよくある質問
タイムカードの手書き運用に関して、よく寄せられた質問をQ&A形式でまとめました。
- Qタイムカードをの記録を紛失したらどうなる?
- Q記入漏れがあった日を無給に出来る?
- Q年棒制はタイムカード不要?
手書きのタイムカードから勤怠管理システムにへの移行がおすすめ
紙媒体のタイムカードは、改ざんのリスクや保管の手間など、どうしてもデメリットの方が大きくなります。
正確かつ客観的な労働時間の記録には、やはり勤怠管理システムの導入がおすすめで、さまざまな打刻方法が可能となるため、多様な働き方に柔軟に対応できるのが強みです。
「勤怠管理システムの選定・比較ナビ」をご利用いただくと、多様な勤務形態に対応できる勤怠管理システムの中から、自社に最もマッチングするシステムを探し出せます。
勤怠管理システムでお困りのあなたへ
・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい
・どのシステムが自社に合っているか確認したい
・システムの比較検討を効率的に進めたい
勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。